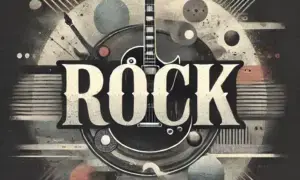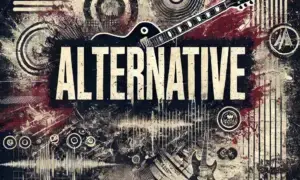Rockabilly/Psychobilly
Rockabilly/Psychobilly ザ・クランプスが1989年に放った初期の毒素全開の『Off the Bone』!ラックス・インテリアの絶叫とポイズン・アイビーの骨太なギターが、50年代のB級映画とガレージパンクを交配させ、禁断のサイコビリーを誕生させた!一度聴いたら逃げられない、真っ赤に充血したロックの真髄がここにある
『Off the Bone』は、1989年にリリースされたザ・クランプスの初期シングルやEP曲を網羅した重要なコンピレーション・アルバムです。当初はイギリスで「3Dメガネ付きのジャケット」という衝撃的な仕様で発売され、彼らの名前を世界に知らしめる決定打となりました。結成当初の荒々しく、かつ妖艶なエネルギーが凝縮されており、パンク・ロックの過激さとヴィンテージな50年代ロックンロールへの偏愛が、もっとも幸福な形で結びついた記念碑的作品といえます。